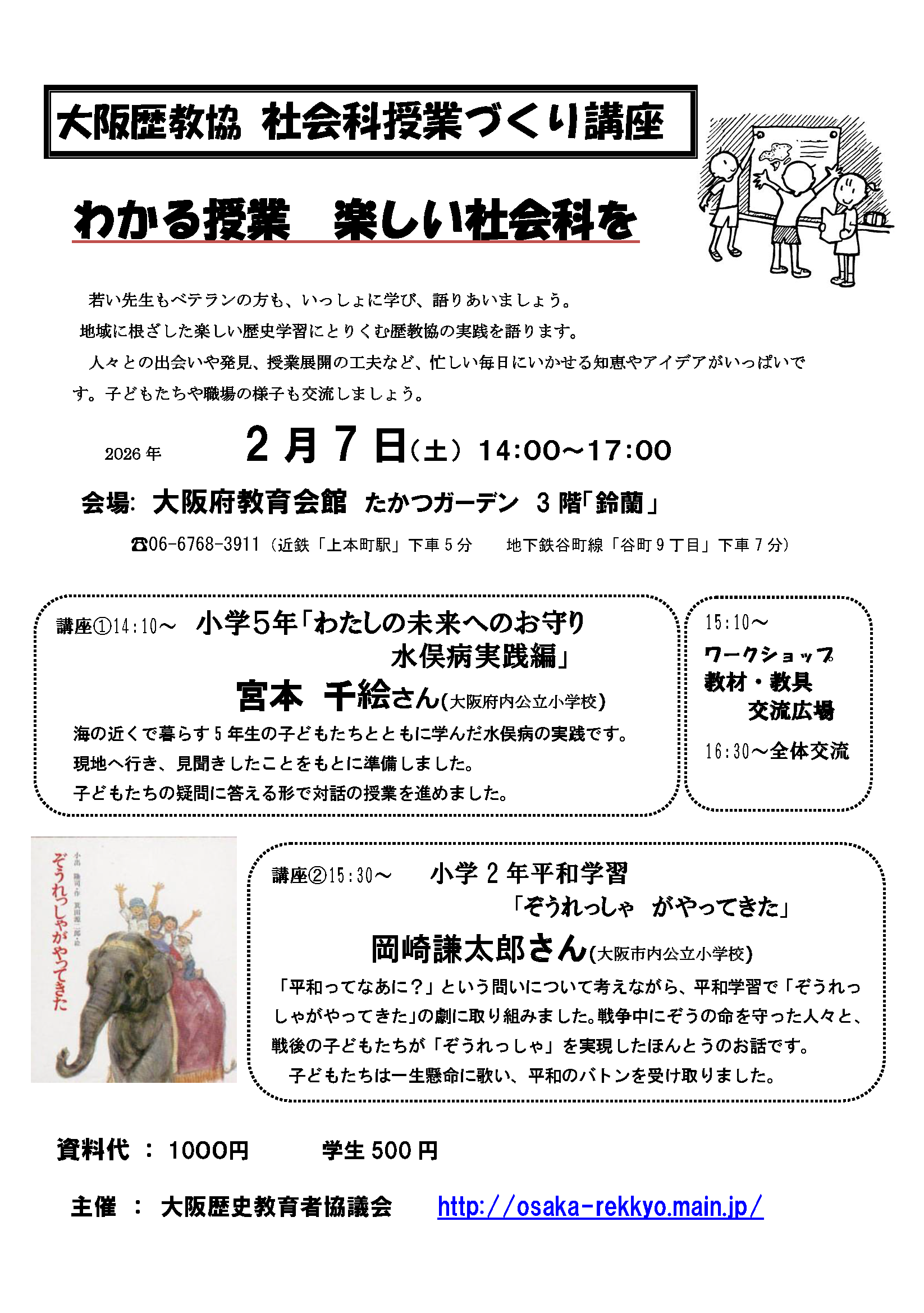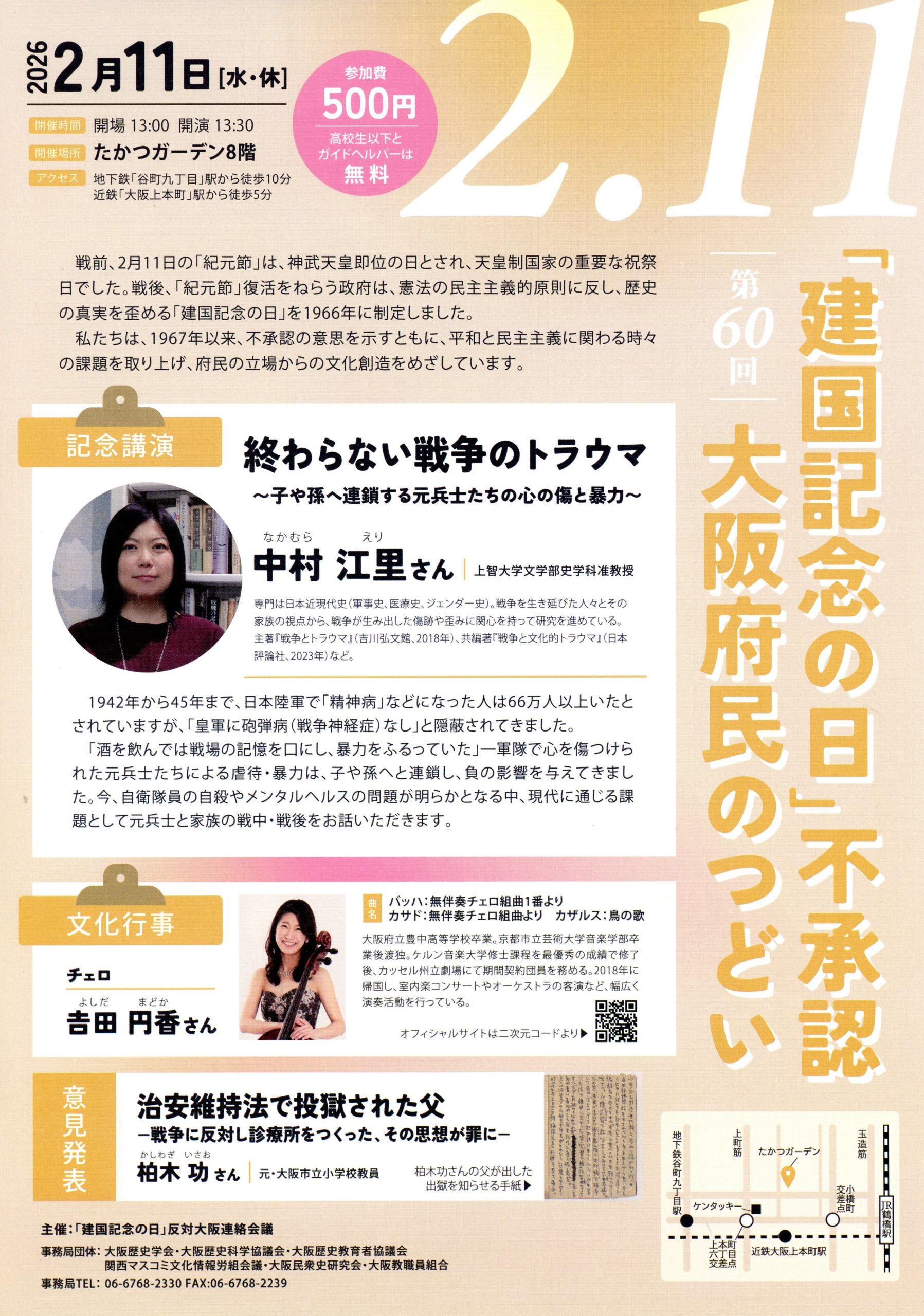日時:2026年2月14日(土)10:00~12:00
場所:磐手公民館集会室4(1階)
テーマ:・参加者担当学年教材研究
・その他何でも
今年は幕開け早々、物騒な軍事作戦が報道され、これからの世界、日本はどう進むのかという不安が生じました。「おめでとうございます」の言葉は飛んで行った気分でした。
社会の動きとは異なり、子どもの世界のほほえましいことが去年最後の例会で報告されました。
ある子が果物の種を教室に持ち込んできました。そのことでクラスの子が次々といろんな種を持ち込んで来たそうです。種だけにとどまらず、植物を持ってくる子も。家の方のアドバイスや協力を得てだとか。
子ども達が互いに刺激し合って、学び合っていきました。思わぬところから、子どもは生活の中から興味関心を広げていくのですね。こんな話が一杯例会で聞ける一年にしたいです。
1月例会は、実施しません。