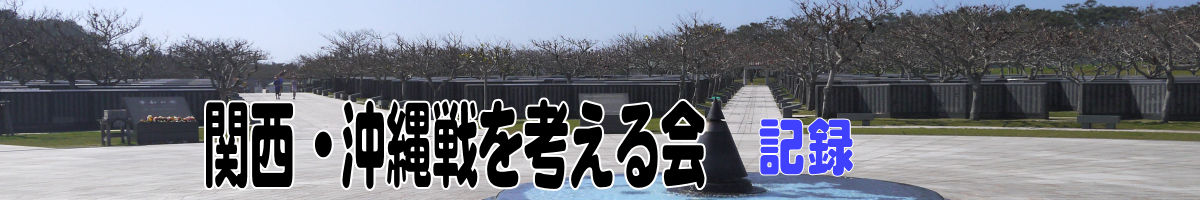第13回講演会 2016年6月17日(金)
『日本にとって沖縄とは何か』 新崎盛暉さん
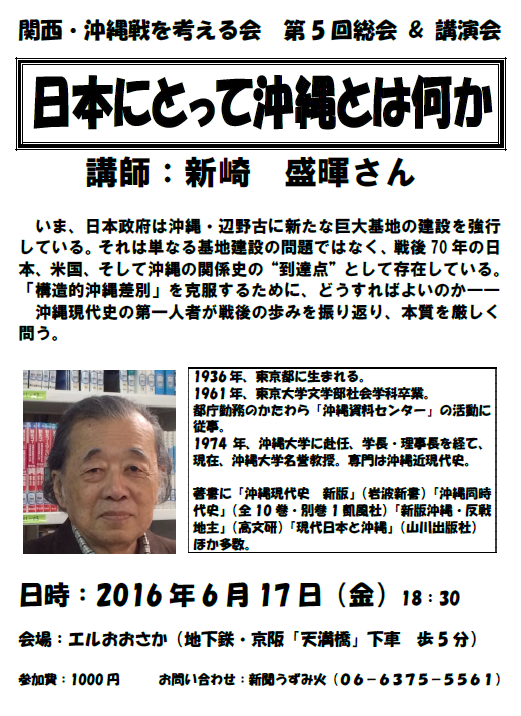
Ⅰ 構造的沖縄差別とは何か
『日本にとって沖縄とは何か』というのは、私が最近出した本のタイトルでもあります。
この本で私が言いたかったことは、沖縄というのは、戦後の日米関係において、または戦後の日本政治と日米関係の中にあって“日本政治の核心部分に位置する”ということです。このことが一番目です。
戦後の日米関係というのは、特徴的には対米従属的な関係として今日まで続いています。
そういう対米従属的な関係が安定的に成り立っているのは、沖縄にその矛盾をしわ寄せしているからです。沖縄に矛盾をしわ寄せすることによって安定している日米関係の仕組みを、私は「構造的沖縄差別」という言葉で呼んでいます。この点が二番目に言いたいことです。
しかし、日本社会ではこの「構造的沖縄差別」の全体像がなかなか具体的に見えていない。特に本土(ヤマト)でこれが見えていない。この構造が可視 化されていないというところに一番大きな問題があるように思っています。それで、この度上梓したこの本で、それをできるだけ見えるようにし、見えるように することによって“沖縄の問題が実は沖縄の問題ではない”ということを、多くの人に、特にヤマトの人たちに当事者意識を持って捉えてほしい、そのきっかけ をつくりたい、というのがこの本の狙いであります。
この本ではいくつかの項目に分けてありますが、「構造的沖縄差別」の仕組みというものが、歴史的にどのようにして成立し現在に至っているのか、ということをまず第一に述べています。
◆沖縄差別の構造
その成立自体は、連合国軍の中心をなしたアメリカの対日占領政策として成立したというのが私の理解です。日本が戦争に負けた時に、日本の政治権力者が一番守りたかったのは何かというと、それは天皇制・日本の国体というものでした。
そして、占領者の方が、そういう日本の権力者が守りたがっている、そして日本人の多くが持っている天皇に対する崇拝の念というものを利用すること が、占領政策、あるいは、その後日本との関係を築いていく上で非常に有効だという判断を持ったというところから日本の戦後が始まったと考えているのです。
アメリカを含む連合国が日本に突きつけたポツダム宣言は日本の民主化を要求していました。民主化と天皇制がどうやって両立するのか、というところで考え出されたのが象徴天皇制です。
つまり天皇から政治的権力・権限を取り去って、国民統合の象徴、シンボルとして日本という国家の最上位に置くということが考え出されたのです。
マッカーサーなど直接日本の占領にあたった連中は天皇制を維持したいと考えていたわけですけれども、一方で天皇には戦争責任があり、国民の崇拝する天皇を残しておくと日本という国家そのものが危険だという議論がアメリカ国内にも連合国内にもありました。
このような議論に対する対案として、天皇制と組み合わせで出てきたのが“非武装国家日本”でした。日本には軍備は持たせない、だから天皇を残しても大丈夫だという説明がなされたのです。
この二つの組み合わせのところまでは戦後の憲法成立過程の議論のなかで指摘されてきたことでした。
けれどももう一つ重要なものが抜け落ちていたのです。それは、沖縄を日本から分離して米軍の要塞、軍事要塞としてアメリカが保持するということで す。つまり、日本という非武装国家を監視したり、周辺から軍事的影響力が及んでくるということを排除するためには、日本ではない沖縄に軍事的なアメリカの 拠点が必要だということだったのです。ですから、この三つがセットになっていたのですが、この三番目はなかなか表面に出てこなかったのです。マッカーサー 自身がこのことを口にしたのは、日本国憲法も成立し施行された後の1947年の6月のことでした。
「アメリカにとって沖縄を米軍の軍事要塞という位置に置くことは重要である。日本は非武装国家の憲法をもったのだから、沖縄の米軍占領に対して異議を申し立てることはないだろう」というようなことをマッカーサー自身が語っています。
それに対して、「その通りでございます。決して異議は申し立てません。アメリカが沖縄を25年ないし50年あるいはそれ以上にわたって支配するこ とは日本の安全にとって必要だと考えています」というメッセージを送ったのが他ならぬ昭和天皇だったわけです。そういう3点セットとして「構造的沖縄差 別」という仕組みはスタートしたのです。
 ◆安保を外から支える沖縄
◆安保を外から支える沖縄
しかし、1949年中華人民共和国の成立、50年に朝鮮戦争が勃発するというアジアの情勢、世界の情勢が大きく変わっていく中で、“非武装国家日 本”でやっていけるかという議論が起こってきます。アメリカ側の立場から見ても、特にマッカーサーは沖縄における空軍基地の重要性を強調していたわけです けどやっぱり地上軍が必要だということになってきます。それで韓国や日本には米軍の補完的な力としての陸上部隊が必要だということから、朝鮮戦争の最中に 米軍の指示によって日本の再軍備がスタートします。最初は警察予備隊という名前の陸上部隊から発足し、講和の直後に海軍ができ、そして54年に空軍ができ て三軍のそろった今の自衛隊ができていきます。
象徴天皇制、非武装国家日本、アメリカの軍事要塞としての沖縄という三点セットの中の「非武装国家日本」の部分は、すでに占領下の段階でアメリカ が使いやすいような国家、「目下の同盟国・日本」として修正されていきます。それが、1952年の対日平和条約で日本が独立するときに「日米安保条約」と いう形で表現されることになるわけです。そして、それまで日本にいた占領軍は、日米安保条約に基づく駐留軍として日本全土に残ることになります。
そのとき、占領軍から衣替えした安保条約に基づく軍隊がどれぐらい日本にいたか。米軍基地の比率でいうとヤマトと沖縄の比率は8:1だったので す。8がヤマトで1が沖縄です。ヤマトには沖縄の8倍、あるいはそれ以上の基地がありました。そしてヤマトでも基地の拡張だとか、軍事機能の強化だとか、 あるいは米軍の犯罪など、今沖縄で起きているようなことが起こっていました。代表的な例を挙げれば、砂川闘争とかジラード事件などが起き、日米間で裁判権 を巡る問題などに発展していきます。沖縄では50年代にさらなる基地拡張に対して、“島ぐるみ闘争”が起こります。そういうことで沖縄とヤマトの双方で呼 応し合うというようなことが起こってきます。戦後、ヤマトにおいて民衆運動のレベルで沖縄が意識されてくるのはこの時期からです。
この時期、日米関係全体としては不安定な関係だったわけです。その不安定な関係を安定した関係にしようとしたのが岸信介による安保条約の改定で す。不平等条約の側面が指摘される旧安保条約を改定して日本を防衛する義務をアメリカに負わせるとか、アメリカ軍が海外の軍事行動に出動する時には日本と 「事前協議」を行わなければならないとか、そういう日本の主体性を強調するような「60年安保改定」が行われたことになっています。
このとき、その前提として、それと組み合わせで行われたのが海兵隊の沖縄移駐だったのです。海兵隊は朝鮮戦争の時期から岐阜県や山梨県にいたわけ で沖縄にいたわけではありません。海兵隊を含む地上戦闘部隊の沖縄への移駐はこの段階で行われたのです。沖縄への基地のしわ寄せの第一段階と言えるでしょ う。また、日本からの米軍の海外出動に対しては「事前協議」の対象にするという「交換公文」が交わされていましたが、今まで一度も「事前協議」が行われた ことはありません。
60年代中期からのベトナム戦争には日本の基地も使われていますが、米軍のベトナム出撃が激しくなっても「事前協議」の対象にはなっていません。 なぜかというと、その出撃部隊は一旦沖縄に移駐してから戦闘作戦行動に出かけているからだと説明されました。沖縄は米軍の施政下であり日本でないから安保 条約の適用地域ではない。したがって事前協議の対象にはならないというのです。このような仕組みが作られていたわけです。このことを私は、「安保を外から 支える沖縄」と言っています。
実際、60年安保改定の段階で基地はどうなっていったかというと、旧安保条約の時に8:1だった、その8の部分のヤマトの基地は四分の一に減り、 沖縄の基地はヤマトからの海兵隊移転などのため二倍になったのです。その結果、8:1の比率だったものが、国土面積の0.6%の沖縄と沖縄を除く日本全体 の基地の比率が1:1になったのです。
◆沖縄返還と沖縄への基地集中
60年代中期にはベトナム戦争が激しくなり、沖縄でも日本でもアメリカ本土でも世界的にベトナム反戦運動が起こります。かつアメリカは財政難に陥 り、沖縄の基地をアメリカが単独で維持することは困難になるという状況の変化が起こります。それで、60年代末から日米間において沖縄を返還するという政 策が動きはじめるわけです。
そもそも沖縄の日本への返還要求は、1950年代の対日平和条約締結の前後から、いわば沖縄を日本から切り離して米軍支配下に置き続けるというこ とに反対する運動として、つまり「平和憲法の下への復帰」というスローガンとともに起こっていたのです。これが沖縄の日本復帰運動でした。
そして、ベトナム戦争の過程で反戦・反基地闘争的色彩を帯びてきてアメリカとしても手に負えなくなってきます。それで民衆の運動や要求を先取りす るような形で沖縄返還政策を立て、日本が沖縄の基地を維持する責任を負うという方向で沖縄返還政策が作られていくわけです。かつての復帰運動は、日米同盟 強化の一環としての沖縄返還政策に反対するように変わっていきます。「沖縄返還協定粉砕」というスローガンの下にゼネストが行われるということになってい きます。
しかし、一日も早く米軍支配下から抜け出したいという意見もあり、沖縄での意見が割れたり選択に迷うようなこともあって、結局は日米両政府の沖縄返還政策が実現していくことになります。
その結果、日本政府としては2倍の基地を国内に抱えることになります。そこで日本本土の基地と沖縄の基地とを合わせていろいろ再編統合していこう という政策が練られ、結局日本本土の基地を三分の一にしていく方針がとられ、1:1であった基地の比率は1:3になっていきます。沖縄も多少は減りました けれども、在日米軍基地の75%が沖縄に集中するという現在の状況はこの沖縄返還後の70年代中期に成立したのです。
そして、沖縄へ集中することによって、ヤマトでは“安保というのは米軍基地と同居することである”という現実が見えなくなっていったといえます。 日本全体で「60年安保闘争」とか、「70年安保・沖縄闘争」というのがありましたが、それ以後、安保闘争などというのはスローガンとしては残っていても ほとんど実態はなくなっていきます。そういう中で、ある意味で安保闘争が残ったのは沖縄だけ、安保といえば沖縄の問題、という形になるわけです。
◆沖縄だけの基地問題に
もう一つ大きな国際情勢の変化に、日中国交正常化があります。
それまでアメリカの基本的なアジア政策は「中国封じ込め」政策であり、沖縄の基地も中国封じ込めの最前線的位置づけでありました。けれどもベトナ ム戦争でアメリカが窮地に陥ったために、ベトナムの後ろ盾となっている中国との関係改善が必要になってきます。さらに、中国とソ連との間で社会主義の考え 方について対立が起こってきたことも利用しながらアメリカのアジア政策に変化が生じてきます。アメリカは「敵の敵は味方」という論理で、突然中国との関係 改善に動き出します。それにあわてた日本は沖縄返還のその年に佐藤内閣から田中角栄内閣に代わり、中国との国交正常化の方向に向かいます。そのために、そ れまで日米同盟を激しく批判していた中国は、安保批判を言わなくなります。それどころか70年代から80年代にかけて中国は、日本のODA援助の最大の対 象国になるという大きな変化があって、中国からの批難もなくなり、日本ではますますもって安保が見えなくなっていきます。
このようなことで、沖縄だけの基地問題、基地問題というのは沖縄問題、安保というのは沖縄問題というようになっていくわけです。
沖縄では「日本復帰」以降も一貫して反基地闘争が続いていました。反戦地主の運動も続いていたわけですけれども、一方で、組織の中央への系列化も 進んでいきます。政党でいえば、例えば沖縄人民党が日本共産党になるとか、いわゆる革新的な諸組織、労働組合なども全国の沖縄県支部、あるいは沖縄県本部 などというような形になっていくわけです。
そういう中央系列化が進む中で沖縄での地域共闘というのが難しくなっていきます。同時に、本土では革新勢力の衰退、安保闘争などがなくなっていく というようなことが進行していきます。沖縄返還後の70年代後半から80年代にかけて本土に系列化されることによって、地域共闘も分断化されていくという ことが沖縄でも起きてきます。
Ⅱ 転機としての1995年
そうした中でも沖縄では、反戦運動はずっと続いていきます。戦後史的に見ても大きな転機になるのが1995年です。95年というのは、日本本土で いえば、阪神淡路大震災やオウム真理教の問題などが記憶に残る大きな出来事だと思いますが、沖縄では9月に、米兵による少女暴行事件が起こって、それを きっかけにして現状変革を求める民衆運動が爆発した年です。
この民衆運動の爆発は、一つには70年代、80年代からずっと続いてきた反戦運動が火種を保持してきたということもありますし、さらには分断化されながら鬱屈していたエネルギーがこの事件をきっかけに爆発したということが言えると思います。
この時期というのは東西冷戦が終わってソ連が解体した時期でもあります。そういうことでいうと、何のために、基地が存在しなきゃいけないのか、安 保がなぜ存在しなきゃいけないのかということを、もう一度問い返される時期でもあったんですね。そういうことを最も切実に実感せざるを得なかったのが沖縄 です。そういう沖縄で事件が起こって、それが引き金になって8万5千人の県民集会に結びついていったのです。
これは50年代中期や70年前後の返還の時以来の大きな転機となることでした。また、ある意味では事件の性格上、保守・革新を超えて、構造的差別 という沖縄だけに矛盾がしわ寄せされているという問題が誰の目にも見えるようになったともいえます。そして基地の整理縮小とか、日米地位協定の改定を要求 する運動のうねりが大きくなっていきます。
この沖縄の動きは日米両政府に対して一定の衝撃力を与えることになりました。
それで日米両政府は、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)というものを作って、いろいろと議論を始めます。そこで出てきたのが、沖縄の基地の整理縮小と日米地位協定の「運用改善」でした。
基地の整理縮小ということでいえば、「普天間返還」を中心にして、沖縄基地の約20%を縮小するというものでした。
この普天間返還の議論が具体化していくにつれて見えてきたことは何かというと、老朽化した巨大な基地をもっとコンパクトな、高度な軍事機能を持つ 基地として再編するということだったのです。しかもそれを日本のカネでやるということでした。その象徴的なものが普天間の辺野古移設です。沖縄はもともと 普天間返還を第一に要求していたということがあります。けれども日米両政府は、そのことを逆手に取った形で、都市の真ん中にある基地を返還することによっ て“危険性を除去する云々”という言い方で、実は人口の少ない東海岸に軍事的機能の高い基地を新設するということになっていくわけです。
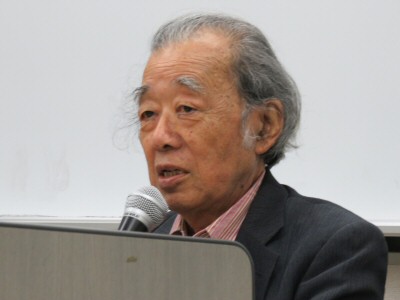
◆普天間問題と沖縄の諸相
95年以降の運動が盛り上がっていく中で、アメリカ側の政策に取り込まれていくような動きも一部には出てきます。少女暴行事件への非難が爆発した とき、これまで革新的運動であったものが、保革を超えた形になったといいましたけれども、ここでは保革の対立というより、政府に一定程度妥協せざるをえな いと考える保守と、一貫した立場を維持する革新と言ったらいいか、そういう部分との間に亀裂が生じ、そういう中で出てきた日本政府との妥協が、辺野古沿岸 沖2キロのリーフ上の「15年使用期限付き軍民共用空港」というものです。当時の岸本名護市長や稲嶺知事、それに当時の沖縄自民党幹事長であった翁長雄志 も民衆からの突き上げと日本政府からの圧力の中でこれを選択したのです。
この案が99年に閣議決定され、2000年代前半には着工するということになり、辺野古沖で櫓を組んで海底調査を始めようとします。それに対する 抵抗運動というのが起こります。加えて2004年に沖縄国際大学に普天間基地のヘリ墜落があり、運動はさらに大きくなってきました。
Ⅲ 「オール沖縄」の形成
◆沖縄保守の変化
そもそも「15年使用期限付きの基地」という、15年たったら使用は終りです、という軍事基地がありえるでしょうか。日本政府は地元とはこのよう な約束をしたものの、アメリカ側との交渉にはこのことを持ち出さない。“地元の沖縄は希望しています”ぐらいのことは言ったけれども交渉には載せない。要 するに時間稼ぎをしながら既成事実を積み上げることでごまかそうとしたわけです。
そしてアメリカにおける同時多発テロの発生から、「対テロ戦争」に対応した「米軍再編」と絡めて日米両国が出してきたのが、2005年の「日米同 盟 未来のための変革と再編」という共同声明です。この中で、この「15年使用期限付き軍民共用空港」などというものは全部チャラにして、翌年5月に、沖 縄の頭越しに発表された「再編実施のためのロードマップ」の中で現在の案が明らかにされてくるのです。
大浦湾から辺野古沿岸を埋め立てて、V字型滑走路を2本作って、弾薬搭載場や強襲揚陸艦の接岸可能な岸壁を造るという計画。強襲揚陸艦というのは佐世保にあってそれと一体化するために接岸できる岸壁を造るということなのです。
この段階で、いろいろな条件を付けて日本政府と妥協して進めようとした軍民共用空港だとか、15年使用期限付だとか、北部振興策だとかいろんな振興策と抱き合わせの政策ではもう沖縄の未来は開けないということを保守の一部が自覚し始めたのです。
自民党幹事長から那覇市長になっていた翁長雄志は、硫黄島を視察して、硫黄島には3000メートルの滑走路のある自衛隊基地があって、普天間をこ こに移したって誰にも迷惑はかけないだろう、というようなことを提案したりします。翁長は小笠原村長や当時の石原慎太郎・東京都知事とも協議をしていま す。そのとき石原慎太郎は、“私は反対はしないけれども、アメリカは受け入れないだろう。アメリカは基地だけが必要なのではなくて、そこにいる兵隊の慰安 とか、住み心地とか、そういうことも要求しているんだから、硫黄島じゃちょっとダメなはず”といっています。結局、石原慎太郎の言うとおり日本政府も硫黄 島案はまともには扱わなかったのでしょう。
一方、稲嶺知事は、“約束が違う、そもそも現在の位置というのは沿岸から2キロのリーフ上というのを検討するときに一度検討した場所であり、そこ は環境上の問題とか、住民の生活への影響とかでさまざまな弊害があって否定されたはずだ”ということで、辺野古沿岸案を拒否し県外移設を主張し始めていき ます。この辺から、底流では保守の側からもこのような動きがでてくるのです。
このような時に教科書検定問題が出てきます。教科書検定問題というのは復帰後何回か起こってくるんですけれども、このとき(2007年)に問題に なったのは、沖縄戦におけるいわゆる「集団自決」に関して、“日本軍の直接的関与はなかった”という検定意見です。それは大江・岩波沖縄戦裁判が起こされ て、原告の陳述を受けてのことだったのです。安倍第一次政権のときの文科省教科書検定意見の中でこれが出てきて、沖縄では非常に大きな問題と受け止められ たのです。
仲里利信さんという当時沖縄県議会議長だった自民党の幹部がいます。彼は現在、「オール沖縄」派の衆議院議員になっていますけれども、彼に言わせ れば、ここが「オール沖縄」の出発点だったと言っています。彼は自民党の幹部でありながらこの教科書検定問題で、自分の幼児期における戦争体験を初めて語 ることによって県議会で満場一致の議決を引き出すという役割を演じることになります。そういう動きが翁長とか稲嶺とか仲里とか沖縄自民党の幹部であった人 たちを含む保守派の中から始まります。

◆民主党政権の成立と沖縄保守
そういう時期に、民主党の政権交代が起こります。民主党は沖縄には全く足場がなかったけれども、沖縄の民衆に、彼らの言葉によると「寄り添う政策」をいろいろ出してきます。その中で出てきたのが、鳩山由紀夫言うところの“普天間基地は国外、最低でも県外”です。
これは確かに沖縄では多くの人に受けました。彼だけではなくて、鳩山内閣の外務大臣になった岡田克也なんかも同じことを言っています。政権交代直前の雑誌『世界』で、「ここで新しい基地の建設を認めたら、もう百年は沖縄に基地が存在することになる」と書いていたのです。
こんな中で鳩山内閣が成立するわけですけれども、結局、自らの発言にこだわったのは鳩山だけだったということになります。一方、沖縄の自民党も総体として国外、県外という方針転換をやるわけです。
これまで自民党中央に押さえられていた中で、民主党政権が成立し、政府自体が国外・県外を言っている状況で、沖縄の自民党も、国外・県外に転換し たのです。つまり、彼らは非常に動きやすくなったわけです。公明党もそうです。鳩山内閣が成立した2009年の12月には、彼ら全部がそういう方針転換を しています。また、そうしなければ選挙で勝てないという事情もありました。1月には、名護市長選挙が待ち構えていたのです。名護市長選挙では今の稲嶺進が 当選することになります。
アメリカ政府や日本の官僚は、鳩山に方向転換を迫りますが、鳩山は翌年の5月まで決着を引き延ばし、その間に何とかしようと思ったに違いないので すが、彼は孤立していきます。しかし、沖縄では、鳩山を激励するという方向に動いていきます。結局、鳩山は国外・県外を実現しないまま政権を放り出すとい うことになりますが、このような流れの中で「オール沖縄」は成立したわけです。
◆安倍自民党政権の強圧
鳩山政権が崩壊した後の民主党は辺野古案に逆戻りします。その後、安倍政権の再登場ということになります。安倍政権は全力を挙げて沖縄自民党や仲 井真県政に方針転換を迫ります。それに屈した仲井真は、2013年の12月に自らの選挙公約を破り「埋め立て」を承認しました。また、その前には沖縄県選 出の自民党国会議員が石破自民党幹事長などの圧力の下で「辺野古も選択肢の一つ」だと辺野古案を認めていきます。
しかし、この仲井真と自民党議員たちの公約破りの転換に対する反発が沖縄の民衆の中に大きく広がっていきます。その翌年の2014年の種々の選挙結果がそのことを物語っています。
それに対して安倍政権は、仲井真知事の”埋め立て承認”を唯一の根拠にして、できるだけ工事を先に進めて反対運動をあきらめさせるという方向で動いていったということになります。
◆2014年、翁長知事の誕生
2014年11月、翁長・那覇市長を保守派の一部が担いで、それに社会大衆党、社民党、共産党まで全部乗っかるという形で、仲井真の再選を許さず、翁長知事を誕生させました。
ここから安倍政権と翁長県政の対立ということになるわけですけれども、翁長は、はじめから強硬策、つまり安倍政権との全面対決に打って出たわけではありません。
“辺野古移設は認めない、あらゆる方法で阻止する”といっていますが、彼が当選した時に何と言っていたかというと、「そうは言っても、とりあえ ず、日本政府ときちんと話し合いをしたい。はじめから辺野古反対をぶつけたら上手くいくものも上手くいかなくなるだろう」と言っていたのです。けれども、 安倍政権の方が、知事の就任挨拶さえ受け付けなかったんですね。翁長と会わないということが数ヶ月続きます。
仲井真の埋め立て承認に法的な瑕疵があるかどうか検証する「第三者検討委員会」を立ち上げるというのが翁長の約束だったんですけど、実際立ち上げ たのは1月末なんですね。彼が就任したのは12月ですからだいぶん遅いのです。それで、現場の活動家や民衆の側から翁長の本気度が追求されるということも ありました。
一方、政権はどんどんと工事を進めていきます。巨大なコンクリートブロックを投下する。それは止めてくれと知事が要望しても防衛局はそれを聞かない。サンゴが損なわれていくという市民の側からの通報があって、沖縄県がそれを検証したいといってもそれも認めない。
そこで県は、漁業規則に基づいて、一週間以内にブロック投下を停止しろという「指示」を出します。
そうすると防衛施設局は、直ちに「行政不服審査法」に基づいて農林水産大臣に、知事の「工事の停止命令」を執行停止にして、それが間違いであるこ とを審査しろという請求を出すんですね。そして農林水産大臣がそれを認めるんですね。これによって知事の指示は無効になりました。
無効にはなったけど、ここで非常に大きな議論が行政学者も含めて全国的に沸き起こります。
そもそも「行政不服審査法」というのは、行政の措置によって国民が権利を侵害されたときに、不服を申し立てるものであって、それを防衛施設局という行政組織が申し立てられるのか、ということなのです。
そういう世論の盛り上がりの中で、初めて官房長官や安倍は、日米会談を控えていたということもあって、翁長との会談をセットすることになります。
この会談で、翁長は極めてトーンの高い、革新派の知事でもあれだけはいえないだろうというぐらい言うべきことを言っていきます。彼は全力投球で菅 と安倍に意見を言っていきます。そこで政権側は逆に懐柔策をとろうとします。それが一月間工事を停止して協議期間を持つということだったのです。
けれども、彼らは工事を止める方針に転換することは一切なしで、日米同盟はどうだとか中国がどうしているからとかの理由を並べ、辺野古新基地を納得しろと言うだけの話です。
他方、翁長としては、沖縄の基地がなぜできたのかとか、普天間基地はどのようにしてできたのか、ということから始まって、その不当性を具体的に主 張します。そして、自分たちが土地を提供したことは一度もない、これは奪われたものだ、それを返すから代わりをよこせ、というのは盗っ人猛々しい、「盗っ 人猛々しい」というのは僕の言葉ですけども、まぁそういう調子で切り返していくんですね。沖縄に対する差別的扱いも指摘します。
そういう中で翁長はついに、第三者委員会の報告を受け「埋め立て承認」を取り消します。
そうしたらまた行政不服審査法なんですね。 今度は、国土交通大臣に申請を出すということになって、知事の権限で何を言おうが工事はどんどん進ん でいくという状況になります。しかもその上で、政権側は地方自治法に基づく「代執行」という訴訟を起こすわけですね。知事の権限を奪って国の権限で埋め立 て工事をやってしまおうという、最後の手段に出るわけです。
Ⅳ 「和解」とは何か、辺野古新基地建設阻止の闘いが意味するもの
司法の独立とか何とか言っても、重要な問題で過去に政府の主張が否定されたことはないということを前提にして、政権側は「代執行訴訟」をやってい くのですが、学者たちの批判的見解が大きく発表され、世論の批判も高まってきます。そんな中で裁判所にある種の“ためらい”が生じたと思われます。それが この代執行訴訟の「和解勧告文」に表れています。
この中で裁判所が言っているのは、国と地方公共団体は独立の行政主体として、役割を分担・対等・協力の関係となるようにしなければならないのにそ うはなってない。対立関係になっている。本来はオールジャパンでアメリカへ協力を求めるべきではないか、ということを言っているのです。国がずーっと勝ち 続ける見通しはないよ、ということも勧告しているわけです。
日本政府は無理なことやっているのです。「代執行」というのは最後の手段だとされているのに、一方では「行政不服審査法」を使って、知事の「承認取り消し」の「執行停止」をやっているのです。それで工事はどんどん進めていくわけです。
自分たち(政権側)が知事の「承認取り消し」を無視した行為をやっておいて、さらに「代執行」というものまでおっかぶせてきたということが、裁判 所側に “いくら何でも”という“心証”を生じさせたと思われます。それで“政府勝訴”の判決は出しづらくなって、そうかといって敗訴にさせられるか、逆に県の勝 訴が出せるか、というようなきわどいところで、裁判所側は「和解」に持ち込むという判断に至ったのだと考えられます。
「和解」の問題についてはいろいろな解釈があります。“ワナ”だと言っている法律専門家もいます。
県は、工事が停止されるということが一応実現するわけですから、「和解」を呑みます。
◆「和解」の意味
ここで、なぜ「和解」という形になったか、その背後には何があるかということを考える必要があります。これは単なる県と国の“法律上の争い”ではないという認識が重要なことです。
翁長知事の言動それ自体も、何が彼をあそこまで突き上げているかという背景を深くとらえていく必要があります。
このことの底流には、現地の闘い、世論、そういうものの歴史的な圧倒的な盛り上がりがあり、今、沖縄は“ここまで”きているわけです。
政府側は、強引過ぎた訴訟手続きが生むかもしれない敗訴のリスクを避けるために和解に応じざるをえなくなっています。
今の状況は、翁長知事の「埋め立て承認の取消」が有効になって工事が停止されているわけです。そんな中で国は「代執行訴訟」のための手続きのやり直しをしようとしているわけです。
この国側がやり直しをしている半年か一年間かの間に、私たちに何ができるか、ということが問われているのです。
何ができるかというのは、現地の闘争や世論がどれだけ大きく形成をされうるか、ヤマトの“当事者意識を持った運動”がどれだけ広がるかにかかっているということです。
確かに沖縄では、この6月19日に県民大会があります。そして、全国的にもいろんな辺野古新基地建設反対の動きがあります。例えば、辺野古の海を 埋め立てるための土砂を搬出しようとしている各地で、土砂搬出に反対する運動が起き、それが全国協議会という形でつながって反対の活動を進めています。ま た辺野古基金という活動基金が何億と沖縄に集まっていて、その7割以上がヤマトから送られてきている。このようなことはこれまで沖縄の戦後史にはなかった ことです。
このような“戦後初めて”というヤマトの動きは、辺野古の闘いの意味が少しずつ理解されてきたということだと思います。また、全国的に問題になっ ている安保関連法案とか、今の安倍政権の動きとまさにリンクしているわけですから、そういう核心部分に辺野古問題があるということが、少しずつは感じ取ら れてきているということかもしれないと思っています。
沖縄と安倍政権の対立は、法律的な闘いとか法廷闘争というだけのものではない。「和解」という事態を引き出している状況。これは現地闘争とか世論の力というものがあってのことだと思うのです。
だから、次にもう一度やり直してくる安倍政権の法的手続きを、法律だけで対応するのではなくて、“闘い”として対応できるかどうか、それが沖縄内に留まることなく全国に広がりうるかどうか、ということが今問われているのではないかと思うのです。